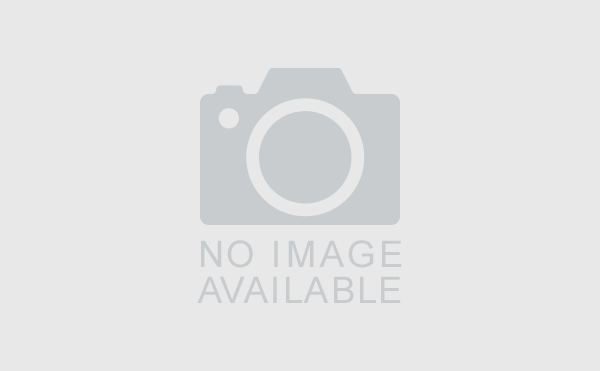6年度第4回 : 航空防衛力整備に係る取組みの状況及び令和7年度航空自衛隊予算の概要について
令和6年度第4回目の講演会(三木会)を令和7年1月16日(木)グランドヒル市ヶ谷において開催した。
今回は空幕防衛課長の富岡慶充1佐と空幕会計課予算班長の東田和也1佐に「航空防衛力整備に係る取組みの状況及び令和7年度航空自衛隊予算の概要について」いう演題でご講演を頂いた。
講演終了後、杉山会長から本講演に対する謝辞と今後の激励の言葉が述べられた。
航空防衛力整備に係る取組みの状況~航空宇宙自衛隊に向けて~
 空幕防衛課長 1等空佐 富岡 慶充
空幕防衛課長 1等空佐 富岡 慶充
1 はじめに
つばさ会の皆様には、航空自衛隊に対して平素からご支援いただき感謝申し上げます。来たる令和7年度は、防衛力整備計画の3か年目を迎える非常に重要な年となります。本日は、令和7年度の航空自衛隊業務計画における主要事業の概要に加え、最近の防衛力整備に関する主要なトピックについて説明させていただきます。
2 航空自衛隊70周年
昨年、航空自衛隊は創設70周年を迎えました。70周年のキャッチフレーズである「大空とその先へ~To the Sky and Beyond~」に示すとおり、今後、航空宇宙自衛隊へ進化すべく、創設当初の任務領域であった空に加えて宇宙まで任務領域が拡大することに対し、各種施策を推進していく所存であります。
また、創立70周年の記念行事の一環として、昨年10月に各国の空軍参謀長等を招へいし、AFFJ(Air Force Forum in Japan)を開催しました。AFFJでは、主に各種会談、多国間協議(InPACT)、JA(Japan International Aerospace Exhibition 2024)見学、そして入間基地見学を実施し、各国空軍との防衛協力・交流を推進しました。先人が築き上げてきた航空自衛隊を更に発展すべく任務に邁進してまいります。
3 令和7年度予算案の概要
防衛力整備計画における主要な7つの柱別等に空自の主要事業について説明します。
①スタンド・オフ防衛能力は、JSM及びJASSMの取得のほか、発射母機であるF-35及びF-2の能力向上等により能力の獲得、強化を行います。
②統合防空ミサイル防衛能力は、リモートアクセス、モバイル化を可能とする次世代JADGE(仮称)の基本設計、下甑島配備のFPS-5及び宮古島配備のFPS7レーダーのHGV対処能力機能付加のほか、PAC-3MSEの取得を進めていきます。
③無人アセット防衛能力の獲得・強化は、離隔した基地等への迅速な補給品の輸送を実施する無人航空機の導入に資する調査・実証試験を行います。
④領域横断作戦能力の強化は、我が国の人工衛星に対する電磁妨害状況を把握する装置の取得に加え、令和8年度のSDA衛星の打ち上げに向けた準備に必要な経費を取得しています。サイバー領域では、基地インフラ及びTNCSにおける監視装置の設置を含む空自クラウドの整備を推進し、電磁波領域では、RC-2を取得し、電子妨害や電子防護に必要な電磁波に関する情報収集能力を強化していきます。
⑤指揮統制・情報関連機能の強化は、指揮官の迅速な指揮に資する空自クラウドの機能向上に係る事業を推進するとともに、地上電波測定装置の換装を実施し、能力を向上していきます。
⑥機動展開能力・国民保護態勢の強化は、KC-46Aを取得する他、操縦者・整備員等の要員養成を行っていきます。また、戦闘機等が民間飛行場等へ分散し、戦力を保全することにより粘り強く戦闘を継続する、機動分散運用の態勢確立に必要な整備器材等を取得していきます。
⑦持続性・強靭性の強化は、JSM等のスタンドオフに係る弾薬を取得するとともに、航空機非可動の解消の他、戦力を保全する観点から分散パッド及び航空機隠蔽用施設等の抗たん化に資する事業を推進します。また、人的基盤の強化として、各種教育訓練に必要な環境・訓練基盤の整備のため、F-35用シミュレータ及びF-2用高性能シミュレータの取得に加え、先進技術を活用した教育訓練環境の整備を行います。更に、航空燃料の確保として、航空燃料調達の安定化を図るため、PFI事業を活用した中間貯蔵施設の整備に係る調査を実施していきます。
空自予算枠外の事業でありますが、早期装備化実証推進事業として、作戦及び戦術に係る訓練等を効果的に行い得る環境構築のため、ネットワーク参加型訓練環境(Live Virtual and Constructive)の整備を行います。
4 最近の防衛力整備に関するトピック
(1)統合作戦司令部の創設
現状における課題として、これまでは、発生する事態に応じ、臨時の統合任務部隊としてJTFを立ち上げていましたが、臨時部隊では、情勢の推移に応じたシームレスな対応が困難であること、また、領域横断作戦を実施する上で統合運用体制が確立されていないこと、そして、インド太平洋軍司令部との調整機能が不足していることが認識されていました。
これら課題を解決する施策として、陸海空自衛隊を平素から一元的に指揮できる統合作戦司令部を創設することしました。創設後の統合作戦司令官の地位・役割は、「自衛隊の運用に関し、大臣の命令を受け、平素から部隊を一元的に指揮」すること、そして「実働部隊である総隊司令官等の各指揮官に任務を付与、また、必要な戦力を各指揮官に配分し、作戦の指揮を行う」こととしています。また、作戦の遂行に加え、部隊の統合作戦能力等の常続的な練成を行います。一方、統幕長の役割は、これまでと変更無く、自衛隊の運用に関する大臣等の意思決定の補佐をすること、軍事専門的見地からの抑止、対処に係る戦略的な方針等を作成すること、そして、軍事専門的見地からの戦略レベルにおける同盟国・同志国等との連携調整等を行います。
統合作戦司令部が創設されることで、平素から統合作戦司令官が、自衛隊の部隊を一部指揮し、効率的かつ柔軟に異なる領域も含めた人員や装備品の配分を行った上で作戦を遂行できるようになります。これにより、統合任務部隊を臨時に編成等せずとも、平素から有事まであらゆる段階においてシームレスに領域横断作戦を実現できるようになります。
(2)宇宙領域に係る取組の状況
2020年5月に宇宙作戦隊を新編し、現在は宇宙作戦群として、府中基地及び防府北基地にそれぞれ部隊を配置し、任務に当たっています。本防衛力整備期間中には、将官を指揮官とする宇宙領域専門部隊を新編するとともに、航空自衛隊を航空宇宙自衛隊とするため、侃々諤々の議論を続けているところです。宇宙空間の安定的利用に対する脅威に対応するため、令和7年度には、宇宙作戦群を廃止し、SSAレーダー及びSDA衛星の運用・維持整備を担う第1宇宙作戦群、衛星妨害状況把握装置及びレーダー測距装置の運用等を担う第2宇宙作戦群及び基地業務群から成る宇宙作戦団(仮称)を新編します。
宇宙領域における態勢整備は、宇宙領域把握、任務保証、優位性確保の3つの段階に区分するとともに、From Space「宇宙から見下ろすもの」、To Space「地上から宇宙を見上げるもの」、 In space「宇宙軌道から宇宙空間を把握するもの」に区分し各種装備品を整備していきます。また、宇宙領域への対応は、国際的な連携も重要です。そのため、 ハイレベル交流や、連絡官の派遣等を通じた米国との連携体制の一層の推進、連合宇宙作戦イニシアチブや多国間机上演習への参加を通じ、各国との連携強化に努めるともに、安定的な宇宙利用のための国際的な取組に積極的に関与していきます。
(3)F35Bの配備等
防衛省は平成30年に、短距離離着陸・垂直着陸機を42機導入することを決定し、その後、機種選定を経てF-35Bを選定しました。当初の計画では、令和6年度に配備される予定でありましたが、納入の遅れにより、令和7年度に配備時期を変更しています。一方で、F-35B配備受入のための臨時F-35B飛行隊は、令和6年度末に新設する予定です。また、昨年10月から11月にかけて米国サンディエゴ沖で「かが」F-35B艦上運用試験を実施しました。本試験には、米国政府(試験チーム)をはじめ、海自、総隊、空幕からも参加し、今後の艦上運用に係る一助を得たと考えています。
(4)対領空侵犯措置
我が国の緊急発進回数は、緊急発進回数が高い水準で推移し始めた2013年度以降、年度全体の緊急発進回数は概ね700回を超える高い水準で推移し続けています。また、中国は年々、活動範囲を拡大させ、かつ頻度も増加させています。
本年8月中国軍のY-9情報収集機が長崎県男女群島沖の領空を侵犯しました。過去に、中国国家海洋局所属の固定翼機や中国海警所属のドローンが領空侵犯をしましたが、中国軍機としては、今回が初めてとなります。また、同年9月には、ロシア軍機が3度にわたり北海道礼文島北方の領空を侵犯しました。この際、フレアによる警告を初めて実施しました。立て続けに、近隣諸国に領空侵犯をされましたが、空自としては、日本の領土・領海・領空を断固として守るとの決意の下、厳正かつ適切な対応を行い、警戒監視及び対領空侵犯措置に万全を期していきます。
(5)北大東への移動式警戒管制レーダー等の配備
我が国の周辺国は、太平洋側での活動を活発化させるとともに、活動域も拡大しております。このため、沖縄本島と宮古島の間やバシー海峡を通過して太平洋へ進出してくる航空機等を警戒監視等する能力の強化は喫緊の課題です。一方で、太平洋側の島嶼部は、警戒管制レーダー及び地上電波測定装置等を十分に設置していないため、警戒監視・情報収集能力を補完する必要があります。防衛省・自衛隊としては、太平洋側の島嶼部に隙のない警戒監視・情報収集態勢をいち早く構築するため、北大東島への移動式警戒管制レーダー等の配備をしたいと考えています。
配備予定の主な装備品は、移動式警戒管制レーダーをはじめ、地上電波測定装置、戦術データ交換システム、対空無線機等であり、島内の2ヵ所に装備品等を配備予定です。
(6)無人機の運用等
将来の戦いに備え、航空自衛隊も無人機の活用について各種検討を重ねています。無人機を運用する意義は、人的損耗を伴わないことから、①高脅威の戦域への投射が可能、②長時間の運用が可能、③有人機に比し安価であること等があげられます。我々も日々進化する無人機の性能や活用方法の情報を入手し、我の戦いにどのように活用していくか今後も検討が必要と認識しています。
航空自衛隊は、一昨年の令和4年12月に偵察航空隊を新編し、同月にグローバルホークが初飛行を実施して以来、態勢整備を進めてきました。令和5年6月に、3機目のグローバルホークが三沢基地に到着し、当初の計画どおり3機体制が完成しました。次に、戦術無人機の状況ですが、スタンド・オフ防衛能力発揮のためには、艦艇や上陸部隊等に関する正確な目標情報を収集することが不可欠です。これを達成するため、高脅威環境下において、相手の射程圏内に侵入し、目標情報を収集し得るISRTアセットとして、今後、戦術無人機の事業等を推進していきます。また、基地警備用無人アセットの取組として、警戒監視の強化、人的被害局限及び省人化を図るため、基地警備用犬型監視システム、いわゆるロボドッグを参考取得し、その有効性を確認するとともに、警戒監視・対処ドローンを実証評価する予定です。
(7)人的基盤に係る取組(処遇改善等)
防衛力の中核は隊員であり、防衛力を発揮するためには、人材を確保することが不可欠であるとの石破総理の強いリーダーシップのもと、処遇改善等の取組を推進しています。
空自全体の充足率は約91%であり、新たな任務付与や、拡大する活動範囲に対応すべく、従来領域の体制の更なるスリム化、省力化・省人化・そして最適化を進めています。その一例として、T-4練習機等の整備業務を部外委託とし、部外力・OB等の活用を進めるとともに、レーダーサイト等の省力化、強固な情報システム基盤を効率的に運用する態勢を構築しています。
隊員の生活勤務環境の改善については、老朽した隊舎及び庁舎の整備を順次行うとともに、シャワーブースの設置、Wi-Fi整備、隊舎の個室化等を積極的に推進しています。また、自衛官の各種手当についても見直す等、既存の制度や考え方にとらわれず、人材確保、処遇の改善等、有効な対策を講じていきます。
最後に、ハラスメント防止のための取組みについてです。有識者会議の提言等を真摯に受け止め、積極的な取組を実施しています。引き続き、ハラスメントに係る正しい知識を定着させるとともに、「しない、させない、見逃さない」を合言葉に、ハラスメントを一切許容しない環境を構築していきます。
5 おわりに
本日、ご参集されている皆様をはじめとして、つばさ会の皆様にもご指導ご協力をいただきながら、年度の防衛予算をしっかりと執行し、空自の精強化を進めてまいります。
令和7年度航空自衛隊予算の概要

空幕会計課予算班長 1等空佐 東田 和也
1 予算編成経緯
防衛力整備計画3年目となった令和7年度予算編成は、例年とほぼ同様の日程で進められ、令和6年12月27日に政府案が閣議決定された。また、令和6年度補正予算については、11月29日に閣議決定され、12月17日に成立した。
【概算要求まで】
令和6年6月21日に「経済財政運営と改革の基本方針2024」、いわゆる「骨太の方針」が閣議決定された。また、7月29日には「概算要求に当たっての基本的な方針」が閣議了解され、概算要求基準が示された。
防衛省は、「防衛力整備計画対象経費については、防衛力整備計画を踏まえ、所要の額を要求する」との概算要求基準に基づき、防衛力抜本強化実現のため、令和7年度中に着手すべき事業を積み上げるとともに、昨年度からの事業の進捗状況を踏まえ、歳出予算の要求額を着実に増額し、概算要求を行った。
その結果、防衛関係費の概算要求は、歳出予算が対前年度8140億円増の8兆5389億円(SACO関係経費及び米軍再編経費のうち地元負担軽減分に係る経費を除き、デジタル庁・各府省共同プロジェクト型システム及び各府省システムに係る経費を含む。)となった。
【政府予算案決定まで】
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、自衛隊の運用態勢の速やかな確保、自衛隊の活動を支える人的基盤の強化や施設整備等を図ることと示された。
防衛省は、これを受けて「自衛隊の活動基盤や災害への対処能力の強化等」として1591億円、「自衛隊等の安全保障環境の変化への的確な対応」として6677億円等、計8268億円を計上し、補正予算が成立した。
また、12月6日に閣議決定された「令和7年度予算編成の基本方針」において、防衛関連として、戦後最も厳しく複雑な状況となっている安全保障環境を踏まえ、国家及び国民を守り抜くため、令和5年度から令和9年度までの5年間で43兆円程度の防衛力整備の水準を確保し、防衛力の抜本的強化を速やかに実現することとされた。
防衛省は、「令和7年度予算編成の基本方針」に基づき、整備計画期間内の防衛力抜本強化実現に向け、令和7年度において必要かつ十分な予算を確保した。
こうして編成された令和7年度予算のポイントとして、財務省は次のとおり言及している。
①令和7年度の防衛関係費は、防衛力整備計画の3年目の予算として、防衛力強化を着実に実施するため、「整備計画対象経費」として8兆4748億円を計上(対前年度+7498億円)。「SACO・米軍再編関係経費」2257億円を含む防衛関係予算全体では、8兆7005億円(対前年度+7508億円)。
②防衛省における装備品取得、研究開発等の事業には、その実現までに複数年度を要するものが多く、目標とする防衛力強化の実現に向けて早期に事業を開始すべく「整備計画対象経費」に係る新規契約額として8兆4332億円(対前年度▲9293億円)を計上。「SACO・米軍再編関係経費」3564億円を含む全体では、8兆7896億円(対前年度▲8907億円)。
③令和6年12月に関係閣僚会議でとりまとめられた「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針」を踏まえ、処遇改善や、営舎内居室の個室化等の生活・勤務環境の改善など、自衛隊の人的基盤の強化に関する予算を計上。
④衛星コンステレーションの構築や各種スタンド・オフ・ミサイルの取得等によるスタンド・オフ防衛能力の強化9390億円(契約ベース)や、PAC―3MSEミサイルの取得等の統合防空ミサイル防衛能力の強化5331億円(契約ベース)に取り組む。加えて、従来不足が指摘されていた装備品等の維持整備や弾薬の確保についても引き続き必要な予算を計上する。また、火薬庫の整備や自衛隊部隊の新編及び新規装備品導入などに伴う施設整備等に取り組む。
⑤研究開発については、日英伊共同で設立したGIGOを通じた次期戦闘機の開発に取り組むとともに、水中発射型垂直発射装置の研究に着手するなど6387億円(契約ベース)を計上。防衛生産基盤の強化についても、引き続き着実に推進。
⑥SACO・米軍再編関係経費については、移設事業等を着実に推進するため、2257億円を確保。
これらのことから、防衛力の抜本的強化は重要課題と位置づけられ、防衛関係費への予算配分が重視されたものと考える。
2 経費の概要
【令和7年度航空自衛隊予算(案)】
以下、防衛力整備計画対象経費について説明する。歳出予算は、対前年度1783億円減の1兆9448億円となった。
歳出予算の内訳として、人件糧食費は、対前年度184億円増の4325億円、歳出化経費は、対前年度1412億円減の1兆1831億円、一般物件費は、対前年度555億円減の3292億円となった。
また、新規後年度負担については、対前年度2472億円減の1兆7595億円となった。
一般物件費と新規後年度負担を合わせた契約ベースでは、対前年度3027億円減の2兆0887億円となった。
【航空自衛隊予算案の総括】
総括すると、前年度までと比較して歳出予算、契約ベースいずれも対前年度から減額となっているものの、防衛力整備計画で計画されている所要の経費は確保され、着実に防衛力の整備が行われている。
令和7年度予算案については、防衛力を5年以内に抜本的に強化するため、スタンド・オフ防衛能力や統合防空ミサイル防衛能力、機動展開能力の向上を図るとともに、装備品の維持整備や弾薬取得、施設整備を促進することができる内容の予算となった。