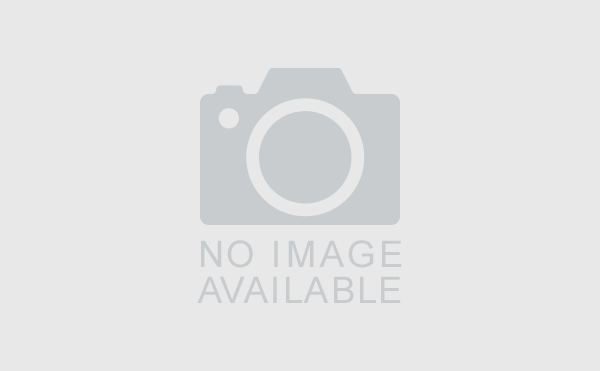6年度第3回:「インド防衛駐在官勤務を終えて」
令和6年度第3回目の講演会(三木会)を令和6年10月24日(木)グランドヒル市ヶ谷において開催した。
今回は前インド防衛駐在官、空幕会計課予算班長の東田1佐に「インド防衛駐在官勤務を終えて」 いう演題でご講演を頂いた。
講演終了後、杉山会長から本講演に対する謝辞と今後の激励の言葉が述べられた。
航空幕僚監部会計課予算班長 1等空佐 東田 和也
(在インド日本大使館 前防衛駐在官)
1 はじめに
インドについては、最近、新聞やテレビで毎日のように取り上げられるようになってきました。2023年に中国を抜き世界第一位の人口を有する国となり、経済成長への期待も高まっている中、世界各国がインドに注目をしています。日本においてもインドへの注目が高まっているものの、インドがどのような国かまだまだ知られていないことも多いと思います。本稿では、インドの概要を外交・安全保障、そして装備協力を中心にご紹介します。
2 インドの現在
インドは現在14億人を超える人口を有し、その平均年齢は約28歳となっています。日本の平均年齢はおよそ48歳、中国は38歳と言われており、若年層の割合が高いです。憲法で定める公用語は22言語、約8割を占めるヒンドゥー教徒以外に、インド国内には1・8億人以上のイスラム教徒、その他にもキリスト教、仏教、シク教などを信仰する人々がいます。地形も北部では5000mを超える山々から、南はインド洋に面した温暖な気候の土地もあるなど、様々な面においてインドは非常に多様性に富んだ国といえます。 日本関連でいえば、インドにおける日本の自動車メーカーのシェアは約5割を占めています。現在、インドに日本企業が1400社以上進出しており、在留邦人も8000人以上いるとされますが、中国と比較するとそれぞれの規模は10分の1程度となっています。インドは日本企業にとって有望な進出先とされているところ、インドからも、さらなる日本企業による進出が期待されているところです。
3 インドの外交姿勢
インド外交は、古くは「非同盟」、現在は「戦略的自律」を追及していると言われています。他国からの影響を受けることなく自国の政策を推し進めようとする姿勢が強く、そのために様々な国との関係を維持しています。具体的には、クワッドで日米豪と関係を強化している一方で、中国、ロシアが参加するBRICSや上海協力機構(SCO)の加盟国ともなっています。ロシアによるウクライナ侵攻後、インドはロシアから安く原油を調達し、本年にはモディ首相がロシアを訪れ、プーチン大統領と首脳会談を実施した一方、国境で対峙する中国を見据え、日本を含め欧米などと連携を強化するなど、特定の陣営に与しないインドの外交姿勢は、他国からすると難しい相手とも見えます。
4 インドの安全保障
インドにとっての伝統的な脅威はパキスタンです。独立以降、インド北部にあるカシミール地方の帰属をめぐり対立が継続しています。直近では、パキスタン国内を拠点とするテロ組織が、2019年2月にカシミールのインドが管理する地域においてテロを引き起こし、インドの警察組織の隊員40名が犠牲となりました。これに対してインドは、テロリストの拠点を、1971年の第三次印パ戦争以降初めて越境して空爆しました。このような強硬な対応が、2019年のインドの総選挙におけるインド人民党(BJP)の勝利の一因となったとの指摘もあります。
一方で、近年パキスタンにかわってインドにとって最大の脅威として顕在化してきたのが中国です。インドと中国は、約3500kmにわたって国境を接していると言われています。1950年代から国境をめぐる対立が始まり、両国はこれまで度々衝突を繰り返してきました。1990年代以降、印中は、国境地帯の安定化を図るため、複数の協定を締結してきました。
しかし、2020年春先以降、中国軍がインド北部ラダックの複数地点において、インドが管理している領域内に立て続けに侵入しました。2020年6月、印中軍がガルワン渓谷において衝突し、45年ぶりに双方に死者が発生する事態となり、両国の関係は急速に悪化しました。問題の解決を図るべく、現地部隊の将官級協議を継続的に実施し、段階的に兵力の引き離しを実施しました。しかし、2つの地点で引き続き対峙が継続していました。ようやく2024年10月にそれらの地点における問題解決に向けた合意がなされ、現在、2020年の対立以前の状況に戻った状況となっています。
これまでインドは、中国を意識し、日米豪との関係を深めてきたと言われています。中国との関係で大きな懸念であった国境をめぐる問題が、2020年の対立以前の状況に戻ったところ、今後、インドはこれらの国々とどのように付き合っていくのか注視が必要であるとの見方もあります。
5 インドの装備政策
ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の統計によれば、インドは、過去10年において世界で最も兵器を輸入した国となっています。インド軍は冷戦期からロシア製兵器を多く使用してきており、現在でもその割合は6割とも言われています。冷戦後、インドはロシア依存を脱却するため、調達源の「多角化」を進めてきました。現在は、米国、フランス、イスラエルなどからも装備品等の調達を進めています。
現在、装備品の主要な調達先であるロシアやイスラエルは、それぞれ紛争を抱えています。インドにとってこのような事態は頭の痛い状況であり、中国と国境地帯で緊張が継続していた中で、調達先の不安定化に伴う影響をできるだけ排除し、自らの手で自国の安全保障を維持できるようにしなければならないと考えています。このような流れは、インドの各種装備品の「国産化」を後押ししています。
国産化の流れは冷戦期からもありましたが、必ずしも順調に進んできたとは言えない状況でした。モディ首相は、2014年の政権発足時から、自国の製造業を強化するため、インド国内での製造を促す「メイク・イン・インディア(Make in India)」という政策を進めてきました。インドと主要国との各共同声明をみると、一見すると経済政策である同政策が、経済の文脈ではなく、安全保障の文脈で言及されています。この点からも、インドは装備品の国内生産を極めて重視していることが分かります。
コロナ禍を通じて、世界各国が中国への様々な物資の依存を改めて認識した中で、インドは「メイク・イン・インディア」に続いて、他国への依存を減らすことを目的とした「自立したインド」という政策を立ち上げました。この流れを受け、インド国防省は2020年8月以降、装備品の国産化リストを5回発表しています。これらのリストにおいて、国産化すべき装備品、部品等を明らかにし、国産化を達成すべき期限も明確にしています。この他、海外から装備品を調達する際にも、インド国内で一定程度製造を行うことを義務付けています。直近の事例としては、米国GE社のF414戦闘機エンジンの国内生産が挙げられます。また、インド空軍はC295輸送機56機をエアバスから調達し、40機がインド国内でインド企業TATAとエアバスが協力して製造することになっています。
インドが、国産化を進めた先に見据えているのは「装備品の輸出」です。2024年9月にインドのシン国防大臣は、インドが既に90か国以上に装備品等の輸出を実現していると述べています。近年の成功例としては、インドとロシアが共同開発した「ブラモス」というミサイルをフィリピンに3億7500万ドルでの輸出を実現しています。
世界の主要国が、インドに対して装備品の移転、現地生産を進める中、インドは日本に対しても、日本の装備品の移転に対する期待を示しています。
6 まとめ
インドは、経済成長の勢いから世界各国から注目を浴びており、国際社会における発言力も高まってきました。インドは、国際社会において無視することができない主要国の一つとなりました。 日印両国は、2000年代半ばから首相が年次で相互往来するなど「自然なパートナー」として政治、経済、安全保障の各分野で着実に関係を強化してきました。日本に後れを取っていた世界の主要国は、急速にインドとの関係強化に動いています。現在、インドが安全保障分野において各国との協力で重視しているのは装備協力です。主要国は競うようにインドに対して装備協力の提案を行っています。このような状況からも、日印が装備協力を進めていくことが今後益々重要となっていくものと思います。
(2024年11月、日印間で艦艇搭載用複合通信空中線「ユニコーン」の移転にかかる目細取極に署名された旨が発表されました。)
〈本稿の内容は個人の見解であり、日本国政府及び防衛省・自衛隊を代表するものではありません。〉