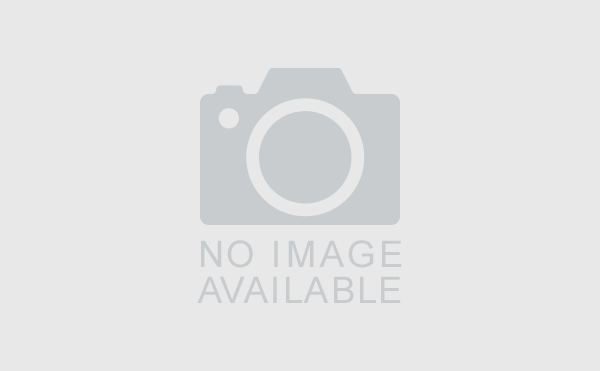6年度第2回:「防衛装備・技術移転」 ~フィリピンレーダー移転から見えたこと~
令和6年度第2回目の講演会(三木会)を令和6年7月18日(木)グランドヒル市ヶ谷において開催した。
今回は防衛装備庁プロジェクト管理総括官の松﨑将補に「防衛装備・技術移転」 ~フィリピンレーダー移転から見えたこと~」いう演題でご講演を頂いた。
講演終了後、杉山会長から本講演に対する謝辞と今後の激励の言葉が述べられた。
 防衛装備庁プロジェクト管理総括官 空将補 松﨑 勇樹
防衛装備庁プロジェクト管理総括官 空将補 松﨑 勇樹
1 はじめに
つばさ会の皆様には、日頃からの我々に対しますご支援に感謝申し上げます。
本日は、防衛装備庁プロジェクト管理総括官としての勤務において、これまで1年半ほど携ってまいりました装備移転、特に、2020年に4基の契約が成立したフィリピンへの警戒管制レーダー移転を通じて経験しました2基の納入、それに係る様々な支援や調整等を行う中で「自分なりに見えたこと」、についてお話させていただきたいと思います。
2 防衛装備・技術移転について
(1)防衛装備・技術移転の位置づけ
新たな国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画、いわゆる戦略3文書において、防衛装備品の海外移転は、「特にインド太平洋地域における平和と安定のため、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出、国際法に違反する侵略等を受けている国への支援等のための重要な政策的な手段」であること、「防衛装備三原則や運用指針の見直し」、「装備移転を円滑に進めるための基金の創設」など、官民一体となって防衛装備移転を進める旨が明示されました。
これまでに、完成装備品の初の移転案件であるフィリピンへの警戒管制レーダー契約のほか、先進国との関係においては、コンポーネント・部品の移転、国際共同研究・開発が行われています。
移転推進のための官民連携の一例として、日本や各国にて開催される国際防衛装備品展示会へ積極的に出展を行っているほか、官民情報共有の場として各種ウェビナーを開催しています。
(2)移転三原則、運用指針の見直し
移転三原則は、装備移転を「禁止する場合」及び「認める場合」それぞれの場合を具体的に明確化するとともに、適正な管理を相手国に義務付けるものです。この運用指針が一部見直されたことにより、グローバル戦闘航空プログラムとして開発される次期戦闘機の海外移転、また、装備品の「部品」の移転が可能となりました。移転可能な「部品」の一例としまして、例えば戦闘機のエンジン、翼などが挙げられます。
3 フィリピンへの警戒管制レーダー移転
(1)移転の概要
2020年、フィリピン国防省と三菱電機との間において、約1億ドル(4基)の契約が成立しました。当該レーダーは、レーダーサイトに配置する固定型(3基)、機動展開が可能な移動型(1基)の2種類です。フィリピン空軍の要求仕様に基づき、三菱電機が、航空自衛隊が運用するFPS︱3レーダーと陸上自衛隊が運用するP14レーダーをベースに新たに設計・製造したものです。
(2)成功の要因
本件の成功は、製造会社、防衛駐在官を含む現地大使館、当時の装備庁のそれぞれ皆さんが一体となり、並々ならぬ尽力をされた賜物であることは言うまでもないことです。ここで触れますのは、本移転に関係するフィリピン側の人々との関係を通じ、私自身が改めてその他の成功要因にもあてはまるのでは、と感じたことです。
大きく4つの要因があると思います。第1に地勢的な安全保障環境の共有です。日比双方の防空識別圏が近接し、東シナ海、南シナ海の安全保障上の価値観をともに共有できる戦略的パートナーシップ関係であること。第2にフィリピンの親日感情です。ASEANの中でも親日感情は群を抜いています。余談ですが、かなり昔のテレビ番組「ボルテスV」はなぜか、特別に人気があり、老若男女みな主題歌を口ずさむことができます。第3には比国軍の急速な国防力整備時期との合致です。冷戦後、空軍力がほぼ空白であった時期から、戦闘機の導入等、急速に防空能力を向上させています。そして第4に防衛協力・交流との緊密な連携です。長年の防衛交流の成果はもちろんですが、レーダー移転の直前には海自TC︱90型機、陸自UH︱1Hスペアパーツそれぞれの供与など装備面での協力の行き足がついていたこと、それに合わせた航空自衛隊とフィリピン空軍とのトップ同士の交流とトップ・セールス、当時の装備庁の人との関係づくりを大切にした相手のニーズに沿った提案等、これらすべてが絶妙にマッチした成果であったともいえます。
(3)フィリピン空軍から感じた彼らの思いと日本への期待
今回、航空自衛隊第1、第5各術科学校、陸上自衛隊高射学校に要員を受け入れて教育支援を行いました。フィリピン空軍は、逐次レーダーが導入されるなか、まさに運用体制(態勢)を構築していこうという途上の段階にあります。日本製レーダーへの信頼と相まって、日本から警戒管制要領などを吸収したいという熱意とともに、能力向上に関する様々な支援を期待しています。また、維持整備能力の向上による可動率確保も彼らの喫緊の課題です。スペアパーツさえあれば運用態勢は大丈夫という過信から、可動率をいかに確保していくかという、マインドセットの変化をも要する課題に直面しています。このような状況からも、日本に対する様々な期待を日々強く感じています。
(4)本移転を通じてみえたこと
フィリピンのような能力向上の過渡期にある同志国への移転を通じて強く感じたことは、「装備移転+α」の覚悟の必要性です。
同志国への装備移転は、同国の運用能力向上そのものであり、そのためには体制(態勢)づくりから本腰を入れて向き合う覚悟が必要であることを強く痛感しました。さらに、移転国側の維持整備能力の向上無くしては、装備品そのもの性能はもちろん、これまでの教育支援や各種交流により行ってきた「日本の支援」いわゆる「日本のサポートのよさ」という信頼さえも獲得できないかもしれません。このような課題をいかに解決するか、これこそが、今後の長期的に見た移転の成功につながるものと考えます。
(5)課題への取り組みの一案として
まず、装備庁として納入後も必要な支援を可能な限り継続することだと考えます。「納入」までが移転ではなく、その後のサポートも移転成功の大きな要素です。必要な教育機会等を継続的に作為していくことにより、装備品の能力向上に貢献することが重要であると考えます。次に、契約に基づいた維持整備による運用態勢の維持です。一部の補用部品のみの契約ではなく、長期的な維持整備についても併せて提案することによって可動率を高めることは、製品の信頼に直結するものであると考えます。3番目に、運用と後方両面における、各種防衛交流等を通じての支援です。各種の専門家交流、幕僚間の協議、術科教育等を効果的に活用した「日本らしい支援」をパッケージとした移転は日本の強みの一つではないかと思うのです。
最後に、このような支援を中長期的に行うオプションの一つとしてOBを活用した支援があると考えます。今回、今後のフィリピン空軍に対する教育等の支援の調査研究として、契約に基づいてOBの方々に参加いただきました。将来的な教育支援の実施の可能性について様々な観点から継続検討してまいりたいと思います。
4 おわりに
本日はフィリピンへの警戒管制レーダー移転を中心に、特に、今後のさらなる移転に向けて、「+α」の支援の重要性等についてお話させていただきました。また、今後の取り組みの一案としてお話させていただいた「OBの活用による教育支援」につきましては、是非とも皆様のお知恵もいただきながら検討してまいりたいと考えます。よろしくお願いいたします。
本日はありがとうございました。