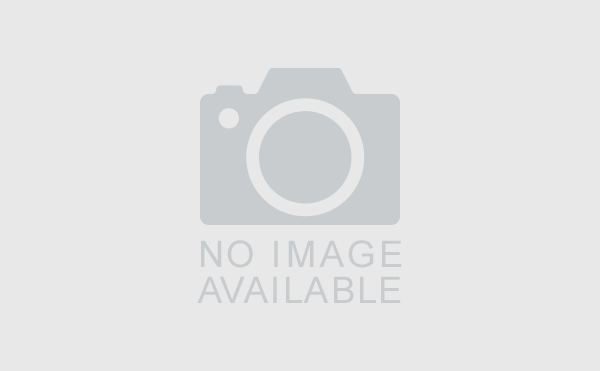6年度第1回:米国防衛駐在官勤務を終えて 〜日米同盟の課題と展望~
令和6年度第1回目の講演会(三木会)を令和6年4月22日(月)グランドヒル市ヶ谷において開催した。
今回は幹部学校副校長の菅井将補に「米国防衛駐在官勤務を終えて〜日米同盟の課題と展望〜」いう演題でご講演を頂いた。
講演終了後、齊藤会長から本講演に対する謝辞と今後の激励の言葉が述べられた。
米国防衛駐在官勤務を終えて〜日米同盟の課題と展望〜
 幹部学校副校長 空将補 菅井 裕之
幹部学校副校長 空将補 菅井 裕之
1 はじめに
本年11月5日、米国で大統領選挙が行われます。先日米紙が日本において「もしトラ」、すなわち、「もしトランプ氏が勝利した場合の日米関係への影響の見極め」が流行語になっていると報道しました。中国の軍事的台頭、ロシアのウクライナ侵攻、北朝鮮による度重なるミサイル発射、さらには中東におけるイスラエルとハマスの衝突と、国際情勢がますます混迷を深める中、インド太平洋地域において最も重要な2国間関係とされる日米同盟は、まさしく岐路に立っていると言えます。本日は最近の米国の状況を踏まえ、「日米同盟の課題と展望」をテーマにお話ししたいと思います。
2 防衛駐在官としての勤務状況
私の勤務は2020年8月、新型コロナウイルス感染拡大によるロックダウン下で始まりました。在米国日本大使館は最大の在外公館であり、防衛駐在官だけで6名も配置されています。今回、私は6名の防衛駐在官と2人の現地職員で編成される防衛班の長として赴任しました。なお、記録をたどればパイロットでない職種の幹部が空自米国防駐官(正)として派遣されたのは私が最初であるようです。
赴任当時、米国は新型コロナウイルスによるロックダウンで閑散としており、大使館での勤務も隔日のシフト制で、防衛駐在官として必要不可欠な人脈の構築が極めて困難な状況でした。それでも、旧知の友人などをつてに細々と情報収集に努めました。特にバイデン大統領が選出された後は、バイデン政権の対中政策はどのようなものかについて有識者の意見を聴取することに重点を置きました。
2021年2月、当時ミシシッピ州コロンバス空軍基地での操縦訓練(SUPT)に参加していた操縦学生が航空事故で亡くなるという事故が発生しました。新型コロナウイルスの制限が強く残る時期で、日本からの出張支援も最小限になる中、ご遺族の米国訪問、当該隊員の帰国、米国における部隊葬への参加などを限られたメンバーで実施しました。非常に辛いミッションでしたが、当時の井筒空幕長にKC―767の派遣を決断して頂き、当該隊員を空自の航空機で日本に連れて帰ることができました。2年目に入り、ワクチン接種が始まったこともあり、現地活動は急速に活発になりました。外交・安全保障においては、米軍のアフガニスタン撤退、ロシアによるウクライナ侵攻といった大きなイベントが続き、調整や情報収集のニーズが一気に増えました。多くの国が将官を派遣するワシントンDCの武官コミュニティを通じ、防衛駐在官を派遣していない国の情報も含めて中身の濃い情報が多く得られました。
3年目に入り、米国が完全にコロナ禍以前に戻る一方、激しいインフレと円安が米国勤務者を苦しめました。特に自衛隊から派遣された連絡官や交換幹部は家計を限界まで切り詰める等、厳しい対応を強いられたと聞いています。ここでの活動の焦点は日本の新たな戦略3文書を米軍関係者や有識者に説明し、フィードバックを得ることでした。今回の戦略3文書は「日本の本気を感じる」として非常に好意的に捉えられました。この戦略3文書の策定により、新しい時代の日米同盟が幕を開けたと感じさせられました。
3 日米同盟の課題と展望
米国での勤務を通じ、今や米国が中国を本格的に脅威として捉えていることがわかりました。2大政党が激しく対立する米国政治においても、安全保障政策は長年超党派の合意によって決定され、中国に対する厳しい目は政権間で大きな振れがないように感じました。また、米国の対中戦略の文脈から、日米同盟がいかに重要性になっているかが理解できます。
一方で、2021年1月の米議会襲撃事件に見られるように、一方的な情報ソースにより他方を「悪」と決めつけ糾弾する風潮が米国内で強くなっており、それを代弁する議員も増えてきます。結果、これまで超党派合意を形成してきた民主党と共和党の穏健派の影響力が低下し、2024年の国防授権法の採決ではついに民主党と共和党で完全に票が割れてしまいました。今後、この傾向が続けば米国国防予算など重要な立法案件が停滞し、米軍の即応性や近代化に悪影響を及ぼしかねません。このように、内政の問題が安全保障に影響するということも今後の日米同盟を語る上で避けては通れない課題と言えます。今後、米国が深刻な分断という内政問題に直面する中、中国という最大の脅威にどう対応していくのか。日本には「アメリカが何を求めるのか?」を問う前に「日本はどうしたいのか」を明確にし、日米同盟をリードしていく姿勢が求められると言えます。それでは、この後私が注目する日米関係のトピックについて2点紹介します。それは、宇宙と装備品の取得です。
4 宇宙における日米協力
2023年12月、日本がイタリア、ノルウェーとともに、連合宇宙作戦枠組み(CSpOイニシアティブ)に参加することが決まりました。日本の宇宙作戦能力の高さや宇宙政策に関する姿勢が高く評価されたものと考えます。一方、航空自衛隊の宇宙作戦能力そのものは極めて短期間に構築されたものであり、米軍、とりわけ2019年12月に新編されたばかりの米宇宙軍の全面的なサポートがあってこそのものでした。米宇宙軍の初代作戦部長であるレイモンド大将は、在日米空軍副司令官として勤務された経
験を持ちます。レイモンド大将は講演会などで、東日本大震災への対応として実施された「トモダチ作戦」を通じ、自衛隊の高い能力と宇宙分野での日米協力の可能性について確信を持つようになったといつも話されていました。レイモンド大将は日本が宇宙作戦能力の構築を進めるにあたっての最大の支援者であり、日本が宇宙作戦を開始するまでの様々な困難を乗り越える上で、彼の存在は極めて大きかったと思います。他方で、今後安全保障分野のみならず、商業分野での宇宙利用が急速に進む中で航空自衛隊がどの分野に資源を投資し、どのように米宇宙軍と連携していくか、課題はつきないと思います。
5 防衛装備品の取得に関する課題
防衛装備品取得というのは、日本語ではあまり聞き慣れない言葉ですが、英語ではDefense Acquisition と表現し、狭義には民間企業との契約等を通じて防衛装備品を導入することを意味し、広義には運用要求の案出や予算の配分など、日本でいうところの防衛力整備そのものを指します。米国では安全保障の主要なカテゴリーとして広く官民で議論され、その担い手は、国家防衛戦略においても「防衛エコシステム」と表現されています。
日米における防衛装備品取得の議論といえば、主にFMS(対外軍事援助)を通じた装備品調達が話題になることが多いですが、FMSは米軍が取得した装備品を外国軍に販売する制度であるため、前提として米国がどのように装備品を取得しているかの理解が必要です。そのため、韓国やオーストラリア、台湾といった、FMSを通じた装備品取得が多い国は、大使館に防衛協力武官(DCA: Defense Cooperation Attaché) を配置し、米国政府や防衛産業と緊密に連携しています。日本も防衛装備庁ワシントンDC事務所を置き、職員を勤務させていますが、米国からの防衛装備品の導入を円滑に行う上では、防衛装備品取得に関する専門的知見をもって対米調整を行うことが不可欠です。また、これはFMSという契約の履行管理だけでなく、より上流に位置する防衛力整備に関する部分においても、米軍のカウンターパートなどと密接な連携を行う必要があります。そのためには、複雑な米国の防衛装備品取得制度について理解する、高い専門性をもった人材の育成が求められます。
6 おわりに
米国の5軍(陸・海・空・海兵・宇宙)と統合参謀本部等のカウンターパートに加え、シンクタンク、防衛産業などで構成されたワシントンDCの「防衛エコシステム」と幅広い人脈を構築することは容易なことではありませんでした。退官された自衛官OBの皆様からも親交のある米軍OBらを紹介していただく等、多くのご支援を頂きました。今後、ここ日本においても、日本の防衛という共通の目的を持つ者同士が組織の垣根を越えて様々な防衛問題を議論できる「日本版防衛エコシステム」が活性化するこ
とを期待し、本講演を締めくくりたいと思います。