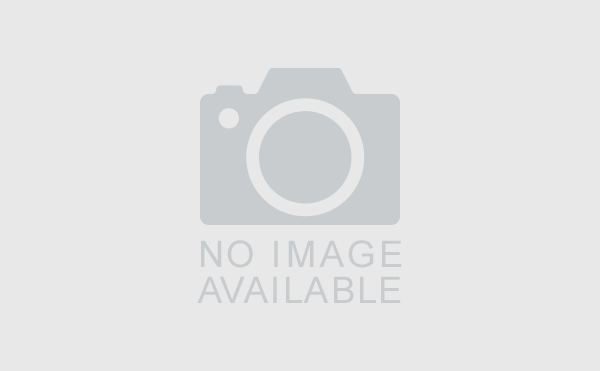7年度第1回:空自に女性活躍推進は必要か-防大女子1期生が33年を経て思うこと-
令和7年度第1回目の講演会(三木会)を令和7年4月17日(木)グランドヒル市ヶ谷において開催した。
今回は幹部学校副校長の金野将補に「空自に女性活躍推進は必要か -防大女子1期生が33年を経て思うこと-」いう演題でご講演を頂いた。
講演終了後、杉山会長から本講演に対する謝辞と今後の激励の言葉が述べられた。
 幹部学校副校長 空将補 金野 浩子
幹部学校副校長 空将補 金野 浩子
1 はじめに
つばさ会の皆様には、平素から航空自衛隊、そして現役隊員の活動に対する多大なるご理解とご支援を頂き、誠にありがとうございます。今回、女性自衛官50周年のタイミングでこのような機会を頂きましたので、防大女子1期生としての33年間を回顧しつつ、空自における女性活躍推進について思うことをお話しさせて頂きます。また、この場をお借りして、これまで様々な場面において、的確なアドバイスにより私たちを導いてくださった多くの先輩方に心より感謝を申し上げます。
私には3人の子供がいますが、このうち長女と次男は航空自衛官です。子連れ単身の機会が多かったこともあり、子供たちの生活の一部に空自があり、様々な機会で自衛官の温かさに接してきたからではないかと思っています。子供が自衛官という同期や後輩女性自衛官を何人も知っていますが、きっと仕事と家庭で線を引くことが難しい母親ならではの影響があるのだと思います。私と同じく防大に進んだ長女は、自衛官である私を否定し、激しく反抗した時期がありました。退職覚悟でぶつかり合い、長いトンネルを抜けた後、長女は私のよき理解者になっていました。双子の息子を出産した後の育児休業中に、官舎の方から「仕事を持ちながら双子を育てるメンタルは普通じゃない。」と言われたことは衝撃的でしたが、後にそれは、家を任された母親が、子育てはもちろん家庭内のことや近所付き合いにも責任を負い、「何かあれば自分のせい。」というプレッシャーを抱える苦しさゆえの言葉だと思い至りました。仕事と子育ての両立は容易ではありませんが、育休後の私は、保育園の専門家による子育てのサポートと自衛官としての活躍の場に加え、「自衛官である母親」でいられる精神的な拠り所が得られました。私は持論として女性が社会進出した方が出生率は上がっていくと話してきましたが、その背景にはこのような経験があり、日本の多くの男性には、子育てと家庭を任された女性の葛藤にも目を向けてほしいと思っています。
2 防大女子1期生としての矜持
私は1992年に防衛大学校に女子1期生として入校しました。国際的な男女平等の流れを受け、日本でも男女雇用機会均等法の制定とともに各省庁における門戸開放が進む中、防大への女性受入れが議論され、「適正規模と活躍が期待できる職域であれば精強性を維持できる。」と整理されたようです。私は偶然にも開かれた扉を前に、「一期生として挑戦できるのは一回きり!」と防大入校に舵を切りました。
入校後は、風呂飯5分、毛布や本は毎日飛ばされ、掃除の後には「姿勢を取れ。」で腕立。服装容儀再点検は金曜日まで。男女の区別なく、先輩方の熱い指導を受けました。その一方、女子学生の誰かが指導されると「だから女は。」、遠泳やカッター訓練などに際しては「お前らにはどうせできない。」、野次馬的な上級生からは「女子学生は防大生じゃない。」という言葉を投げかけられ、「じゃあ、何故女性を採ったの!?」と国の施策と現場の意識とのあまりの乖離に腹立たしくもなりましたが、そんなことを悩んでいる暇はないので「最初はこんなもの。とにかくやるしかない!」と割り切りながら、受けた指導は必ずその日に女子学生全員で共有し、体力不足を補うために日々消灯後の部屋で腕立てや肩車スクワットをしました。「女子学生が入って防大が甘くなったと言われたくない。」という上級生の言葉は、そのまま私たちの思いでもありました。当時の指導教官や1期生の対番を担った38期の先輩方は、いち早く既存の価値観を切り離し、男女関係なく寄り添い、女子学生を孤立させず、甘えさせず、きめ細やかかつ大胆に、私たちを普通の防大生に育てて下さいました。防大生は将来の幹部自衛官ということすら理解していなかった私が、防大生活を通じて任官意思を明確に持つことができたのも、性別の隔てなく士官候補生を育てる防大教育の素晴らしさがあったからだと思います。
任官後に感じた空自の女性に対する空気は思いのほかソフトでしたが、女性幹部として初めてとなる場面には大小様々なハードルがありました。初任地であった201飛行隊のMRでは日々質問の嵐でしたが、実は「女性の付幹部が来るけど甘やかすな。」と申し合わせていたそうです。おかげで私は整備の現場に足しげく通い、整備員を心から信頼し、尊敬できる整備幹部になれました。3人の子連れ単身で臨んだCSCでは、私だけが子供が病気になった際の対応計画を求められたことや、CSCを卒業し補職された空幕装備部で「子供が3人いるようだが、24時間365日対応できるのか。」と問われ「自分も自衛官です。しっかり対応します。でも、何故私だけに聞くのですか?みなさん毎日24時間そこにいるのですか!?」と聞き返したことは、今は笑い話です。修理隊長として着任した際には、年配の分隊長が斜に構えて私の話を聞いている姿を目にし、「やっぱり。」と一瞬落胆しつつも、「しっかりやって、隊長に男女は関係ないことを当たり前にしていくしかない。」と原点に戻りました。防大女子1期生としての矜持は、今に至るまで、私の自衛官人生の矜持でもあります。
3 航空自衛隊における女性活躍
空自における女性自衛官の比率は、2023年度末で10%を超えました。防大に続き、航空学生への女性の受け入れ、採用時の女性枠や配置制限の撤廃など、空自は女性への門戸を開き続けてきたものの、男性が採れる時代に女性を積極的に採用するには至らず、長らく女性の採用上限数が設けられてきました。ところが、募集対象人口の減少により男性の採用数が頭打ちになると、省内で「女性活躍推進」の名のもとに女性の教育・勤務・居住環境、受け入れ態勢の整備や働き方の改革が急加速し、女性比率も急激に上昇しました。50年かけて10%に達した女性比率が、数年後の2030年には16%まで拡大する勢いです。空自は現在「空自の精強化及び空自の進化の達成に必要かつ優秀な人材を安定的に確保し、限られた人材を効果的に活用していく。」との考え方のもと、「性別を問わず全ての隊員が働きやすく、かつ、活躍できる組織の基盤の確立」のために各種取り組みを進めています。令和6年の防衛白書には「活用できていない最大の人材源は、採用対象人口の半分を占める女性」と表現されており、未だ数としての女性の価値に注目がいきがちですが、空自が任務を支える真に価値ある人財としての女性活躍を期待しないのであれば、女性比率の上昇を手放しで喜ぶことはできません。
4 日本における女性活躍の現状
内閣府の資料によると、日本の女性の年齢別労働力率は先進諸国の中でも顕著なM字カーブ(出産・育児期に低下)を描いており、正規雇用比率も男性に比して低く、L字カーブとなっています。主な理由は「家事、育児、介護と両立しやすいから。」であり、背景として、日本の夫が家事・育児にかかわる時間はそれぞれ1時間程度と国際的に低水準であることが挙げられています。なお、夫の家事・育児時間が長いほど、妻の継続就業割合は高く、第2子以降の出産割合も高い傾向にあります。また、日本の男女で総労働時間に差はないものの、女性の無償労働時間は男性の5・5倍、日本の男性はほとんどの時間を仕事に費やしているのです。さらに、日本人の性別役割に対する無意識の思い込みについて調査したところ、男性の方が女性よりも性別役割意識が強く、男性が女性に対して考える上位10項目には、「女性は感情的になりやすい。」「育児中の女性は重要な仕事を担当すべきでない。」「女性は弱く、守らなければならない存在である。」「共働きでも男性は家庭より仕事を優先すべきだ。」というものがあります。未だ、日本の社会で女性が男性と肩を並べて活躍するには厳しすぎる現実があることが見えてきます。
5 空自に女性活躍推進は必要か
 先般、防大女子学生と懇談をする機会を得ました。(その時の写真です。壮観ですよね。)1期生入校以来、長い間40名程度であった女性の採用枠は、2022年に70名、2023年からは100名と急激に拡大されました。防衛省における女性活躍推進の取り組みの象徴なのかもしれませんが、過剰な女性枠の設定は、能力に応じた採用を損ない、現場における男女の分断を拡大させる危険性をはらみます。学生との懇談の中で、「女性が将官を目指す上で大事なことは何か。」「男性が多い職場でどのようにリーダーシップや存在感を発揮したか。」というような質問がありました。志の高さに感服する一方、33年もの共学の歴史を刻んだ防大において、性別差を意識する学生が多いことに驚きました。また、この3月にCSCを卒業した女性幹部は「女性活躍」「女性登用」という言葉によって、意図せず別トラックに乗せられることへのプレッシャーや不安を抱いていました。
先般、防大女子学生と懇談をする機会を得ました。(その時の写真です。壮観ですよね。)1期生入校以来、長い間40名程度であった女性の採用枠は、2022年に70名、2023年からは100名と急激に拡大されました。防衛省における女性活躍推進の取り組みの象徴なのかもしれませんが、過剰な女性枠の設定は、能力に応じた採用を損ない、現場における男女の分断を拡大させる危険性をはらみます。学生との懇談の中で、「女性が将官を目指す上で大事なことは何か。」「男性が多い職場でどのようにリーダーシップや存在感を発揮したか。」というような質問がありました。志の高さに感服する一方、33年もの共学の歴史を刻んだ防大において、性別差を意識する学生が多いことに驚きました。また、この3月にCSCを卒業した女性幹部は「女性活躍」「女性登用」という言葉によって、意図せず別トラックに乗せられることへのプレッシャーや不安を抱いていました。
1期生はじめ初期の女性は、「とにかくやって道を開く。」ことが至上命題であり、ある意味、後輩たちに両立していく上での知恵やアドバイスは提供できても、ロールモデルとしては適当ではありません。しかしながら、10%を占めるまでになった女性自衛官の多くは、いち日本人として、数ある選択肢の中から防大や空自への道を選択してくれた人財であり、性別による役割を期待されて入隊してきたわけではないはずです。引き続き、環境の整備は必要であるものの、制度上男女の処遇の差がなく、日々の職務の成果に性別は関係ないことを経験してきた空自において「女性活躍推進」を掲げ続けることは、男女差への注目度を助長し不公平感を抱かせ、個々の実力の適切な評価と更なる発揮を阻害しかねません。実際、職務上の性別は個性の一部分でしかなく、体力1級と7級、身長180㎝と160㎝、右利きと左利き、A型とB型、大阪人と東京人、という差のほうが影響は大きいのかもしれません。必要ならば、体格や能力別の基準を明確に設ければよいのです。空自は真に「優秀な人材を確保し、性別を問わず活躍できる組織」へと進化していくために、もはや「女性活躍推進」を手放すべきではないでしょうか。
6 おわりに
意識改革と具体的な行動には世代を越えた努力が必要です。親世代の価値観は、子どもの世代の価値観に影響を及ぼすものであり、つばさ会の皆様が、女性が男性と肩を並べて活躍するには未だ厳しい日本社会の変化に関心を持ち続け、子供世代をサポートすることこそ、自衛隊における性別を問わない活躍の実現を後押しするものと信じています。つばさ会のみなさまの更なるご活躍を期待しています。